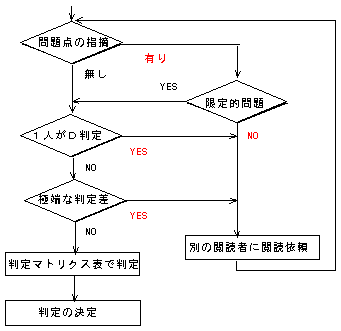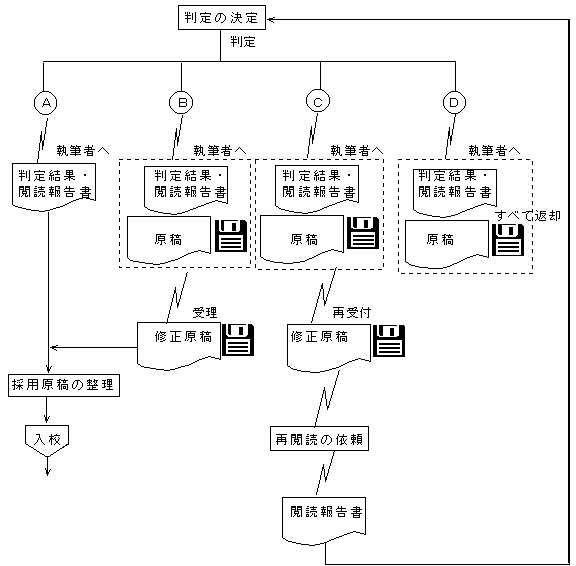1.入稿 |
(1) | 原稿一式の整理作業
編集幹事は最終原稿を受け取り後,入稿に向け原稿一式の整理作業を行う。なお,この整理作業の一部を編集予算内で外部に委託しても良いが,最終のチェックは編集幹事が行う。 |
1) | file(FD)の整理
すべての掲載原稿を,統一されたフォーマットに揃える。 |
| ① | 〈引用文献〉の後に1行空け,原稿受理年月日を行末揃えで(2001.10.10 受理)の形で記入する。 |
| ② | 執筆要領に従った原稿になっているかをチャックし,違反があった場合は修正する。なお,この修正には執筆者の了解を得る必要はない。 |
| ③ | 2段通しのfileでは,原稿の区分,執筆者名,タイトル,Abstract・要旨文章,所属,キーワードは左詰にし,Abstract,要旨の見出しは中央揃えにする。また,要旨の見出しは,「要」「旨」の間を1字空け「要 旨」と表記する。 |
| ④ | タイトル,氏名,所属など級数が本文と異なる箇所であっても,文字の大きさを変える必要はない。原則として,これらの指示はすべてプリントアウトした原稿に朱書きする。 |
| ⑤ | 所属等の上付文字は,「*ナンバー」を半角で記入した後に上付にする。はじめの入力が半角と全角では印刷で出てくる上付後の大きさが異なるので,この点について統一がとれているか否か注意する。 |
| ⑥ | 本文のfileは,図表の位置や編集上の指示を書き込むスペースを充分にとるため,左右の余白を広く設定する(左右とも50㎜程度の余白が適当)。 |
| ⑦ | 2段通しのトップページのfileと本文のfileとを分け,体系的なfile名をつける。このfile名はそれまでの作業段階で付したfile名とは変え,混同の可能性が生じないようにする。 |
2) | 表紙・裏表紙の作成
fileの整理と同時に,表紙・裏表紙を作成する。表紙・裏表紙のためのデータは,執筆者から提出されたFDのデータを掲載紙の体裁にあわせて整えたものを用い,できる限り新たに入力することは避ける。 |
3) | 原稿一覧表の作成
以下の様式で,掲載原稿の一覧表を作成する。 |
4) | 原稿の整理 |
| | ① | 原稿1ページ目の左上に原稿ナンバーを水色で書く。 |
| | ② | プリントアウトした原稿に,執筆者が記した図表の挿入位置,文字の種類,上付・下付の指定を転記するとともに,タイトルのゴジック指定など必要な指示を朱書きし,ホチキスでとめる。 |
| | ③ | 図表の適切な縮尺,『開発学研究』●巻●号,執筆者名,タイトルの冒頭…を記入する。ここで縮尺を記入する際には,同一論文では図表の文字サイズができるだけ同じになるように配慮する。また,図表の文字のサイズは,本文の文字サイズより小さくなるようにする。なお,図表は紙面を横に用いることはせず,どうしても1ページに収まらない大きな図表の場合には,見開きページにする。 |
| | ④ | 原稿№順に原稿を揃える。 |
5) | 入稿予定日の連絡
原稿の整理作業の途中で出版社に入稿の予定日を連絡する。 |
(2) | 入稿 |
1) | 入稿
以下の一式を揃え,出版社に入稿する。 |
| | ① | 原稿一覧表 |
| | ② | 原稿一式(本文,図表,図表キャプション) |
| | ③ | 原稿データの入ったFD |
| | ④ | 出版社に渡すものの一覧表・注意事項等を記した文章(編集員長名で文章を作成)。 |
| まとまって入稿後に原稿を追加して入れることは,原則として行わない。 |
2) | 校正予定の確認・連絡
入稿時,ないしは入稿後数日以内に校正の予定を確認し, |
| | ① | 執筆者 |
| | ② | 編集幹事 |
| | ③ | ホームページ管理委員会 |
|
に連絡する。なおホームページ管理委員会への連絡にあたっては,ホームページに掲載する付帯的な連絡事項・注意事項等も併せてe_メイル等で連絡する。 |
(3) | 別刷り製作部数一覧表の作成
別刷り製作部数一覧表を作成し,確認の必要がある場合は執筆者に確認を行う。
初校前に確認できなかった場合は,初校の時に確認を行う。初校時に申し出がない場合は,特別な場合は除き別刷り不要との意思表示とみなし,以後の申し込みは受け付けない。
|
2.初校 |
(1) | 初校出しの準備
初校出しに向けて, |
| | ① | 送付用封筒 |
| | ② | 返信用封筒 |
| | ③ | 送り状 |
| | ④ | 原稿
|
|
は事前に準備しておく。 |
(2) | 初稿出し作業への編集幹事の招集
初校出しの日程が確定したら,直ちに編集幹事に初稿出し作業の集合日時を連絡する。
いかにやりくりしても初稿出し作業を行うことができない編集幹事は,その旨を速やかに編集作業の中心になる幹事に連絡する。 |
(3) | 初稿出し
編集委員会に初校ゲラが到着したら,直ちに以下の初稿出し作業を行う。 |
1) | 初校ゲラのコピー
少なくとも3部(執筆者・編集委員長・編集幹事用)コピーを取り,執筆者への送付用に論文毎にホチキス留めを行う。校正の朱書きはコピーに行い,出版社から届いたゲラへの書き込みは校正結果の集約時とする。 |
2) | 執筆者への初稿出し
執筆者には次の一式を揃え,初校を送付する。 |
| | ① | 送り状(返信締切・返送先を落とさないように留意する:既定の書式を用いる)。 |
| | ② | 初校ゲラ |
| | ③ | 原稿一式(執筆者から送付された原稿) |
| | ④ | 返信用封筒(依頼原稿の場合は返信用切手を添付する) |
|
なお,レイアウトに関する執筆者からの指示は初校戻しまでとし,初校戻し以降の申し出は受け付けない。 |
3) | 編集委員長・編集幹事への初稿出し
編集委員長にはすべてのゲラを,編集幹事は分担してゲラをチェックする。できる限り1論文について2名以上の編集がチェックするようにする。なお,文章については執筆者がチェックを行っているので,編集幹事はレイアウト,規定と異なる点を中心にチェックする。引用文献の書き方が既定と異なっていたり,文章中の引用文献と〈引用文献〉に示された文献が一致しないこと,図表の数値と本文中の数値が微妙に違っていることがよくあるので,編集幹事はこの点を意識的にチェックする。この点検で編集幹事が判断できない箇所が発見された場合は直ちに編集作業の中心になっている幹事に連絡する。疑問点の報告を受けたら,速やかに執筆者に問い合わせを行う。
用語・用字については,論文単位に統一がとれていれば良しとする。一論文中に表記のゆれがある場合は,多く使用されている方で揃える。また,俗語で用いられている略した用法は,学会誌掲載に適するケースを除き正確な用法に改める。 |
(3) | ホームページ管理委員会への連絡
初稿出し作業が終了したら,初校の予定を含めホームページ管理委員会に連絡する。なお,校正に関わる点でホームページに掲載する情報があった場合は併せてホームページ管理委員会に連絡する。 |
(4) | 初校戻し |
1) | 編集幹事の招集
編集の中心となる幹事は,初校戻し作業を行う日時を確定し,編集幹事を招集する。時間調整しても作業に参加できないときは,速やかにその旨を編集作業の中心になっている幹事に連絡する。 |
2) | 初校結果の集約
編集幹事会で,執筆者・編集委員長・編集幹事から提出された初校ゲラをつき合わせ,修正点が問題ないかを確認し,問題がない場合は朱の入った箇所を出版社から受け取った校正ゲラに転記する。修正によって問題が生じる場合は,編集幹事で修正の却下(修正により規定違反になる場合や,文意が不明になる場合など)を含め対応方法を協議し,編集委員長が決定する。この対応方法については,執筆者から問い合わせがない限り,対応方法を変更したことについての連絡は原則として行わない。 |
3) | 初校戻し
出版社に,以下の一式を揃え初校を戻す。 |
| | ① | 初校ゲラ |
| | ② | 出版社から戻ってきた原稿 |
| | ③ | 別刷り製作部数一覧表 |
| | ④ | 引き渡しの仕様書
|
3.再校 |
(1) | 編集幹事の招集
初校戻し時,ないしはその後2~3日以内に再校出しの日時を確認し,再校出しに関する作業を行う日時を決め,編集幹事に招集の通知を出す。どうしても再校出しの作業を行えない編集幹事は,その旨を編集作業の中心となる幹事に速やかに連絡する。 |
(2) | 再校出し
再校ゲラが編集委員会に着き次第,直ちに以下の再校出し作業を行う。 |
1) | 再校ゲラのコピー
再校ゲラを少なくとも2部コピーし(編集委員長・編集幹事用),幹事校正用に論文毎にホチキス留めをする。 |
2) | 編集幹事で分担し再校を行う。なお,幹事校正では,少なくとも2名以上で同一論文のチェックを行うようにする。 |
3) | 幹事校正では,誤字・脱字,執筆要領違反,体裁の統一性,レイアウトを中心にチェックを行う。 |
4) | 再校出しが終わったら,ホームページ管理委員会に再校に入ったことを,再校戻しの予定をあわせて連絡する。 |
(3) | 再校戻し |
1) | 幹事校正期間は再校出し日を含めておおよそ4日間程度とし,5日目には再校結果を集約し,遅くとも6日目には再校を出版社に発送する。 |
2) | 再校結果を集約するために再校出し時,またはその翌日に編集幹事招集の連絡を行う。再校戻しの作業が行えない編集幹事は,その旨を速やかに編集作業の中心になっている幹事に連絡する。 |
3) | 編集幹事会で,編集委員長・編集幹事から提出された再校ゲラをつき合わせ,修正点が問題ないかを確認し,問題がない場合は朱の入った箇所を出版社から受け取った再校ゲラに転記する。なお,再校での修正は,執筆者から問い合わせがあったとき以外は執筆者に連絡を行わない。 |
4) | 再校結果の集約が終わり次第,出版社へ再校ゲラを戻す。 |
(4) | 配送先・代金請求先の確認
再校戻し時に,本誌,別刷りの送付先,および代金請求先といつ請求したらよいかの確認を行う。編集委員会宛にも請求書の写しを送付するように手配する。
|
4.念校 |
念校は,特別に問題がないかぎり出版社での責任校正とし,疑問点をFaxでの連絡で対処する。
念校終了と同時に,納品の日時を確認し,発送担当,会計担当等に連絡をするとともに,別刷り等の送付準備を行う。 |